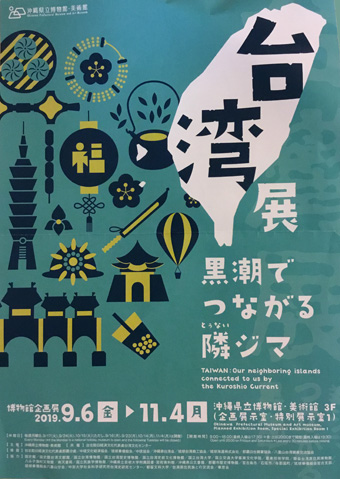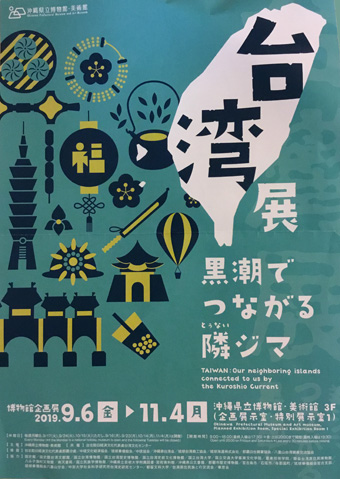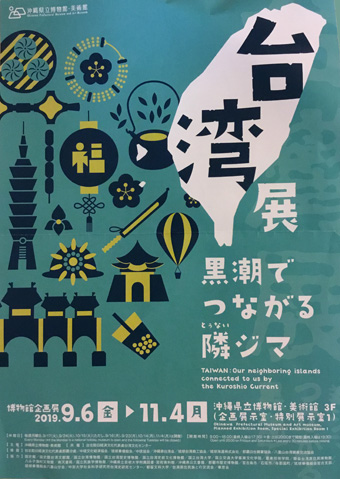コンテンツへスキップ
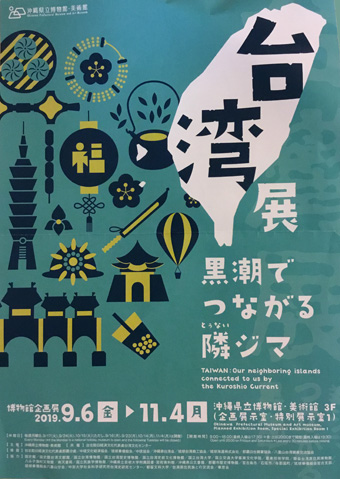
沖縄県立博物館で2019年9月から11月上旬にかけ、企画展として台湾展~黒潮でつながる隣(とぅない)ジマ~が開催されました。地理的には八重山諸島と100キロメートル余りで、明治時代から第二次世界大戦まで50年間は特に活発に交流が行われた背景があります。沖縄の製糖やパイナップル産業の発展にも大きな貢献をもたらしたとされています。ミュージアムショップで、沖縄タイムス社が新書版の文芸叢書シリーズとして出版している「インターフォン(松田吉孝著)」を購入しました。沖縄-石垣-台湾のアイデンティティをテーマにしたフィクションです。特に主人公の女性(石垣島出身、因みにルームシェアの同性の友人は与那国島出身)が高校卒業の時に担任教師に言われた「島の外に出ると、島のことがよく見える」が印象に残りました。
戻る
2019年10月31日: 首里城の火災、言葉になりません。ただ、ただ、悲しいです。
2019年11月17日: 首里城の復興には建材の調達なども含めて多くの課題がありそうですが、再び荘厳な新首里城が姿を現すのを楽しみにしています。
 • 那覇と台湾
• 首里からみる那覇港の眺め
• 古き良き佇まい
• 市場での感動
戻る
• 那覇と台湾
• 首里からみる那覇港の眺め
• 古き良き佇まい
• 市場での感動
戻る
個人が、仲間と一緒に他の地域の特産品、異文化を楽しむ、それができることはとても大切なことです。一方で、自分達の特産品や文化も他地域のヒトに楽しんで貰うように仕掛けを作って情報を発信しましょう。勿論個人で仕掛け作りができるものではなく、各自治体や企業がすることになります。ここで考えてみて下さい。他の地域のものを楽しむのは個人、自のものを売りこむのも基本単位は個人で、両者の動機も気軽で、楽しくて、頑張ることではなくて… 。武力ではなく経済的に有利になるためには、他にないものを発掘する、発信することに尽きるというのが本編の結論です。
戻る
姉妹(友好)都市としての提携や代表団などを通しての交流会が各地域で積極的の行われています。個人的な旅行も勿論楽しみですが、ヒトを通して他の地域をよりよく知るためには、交流会などのイベントに参加してみるのもお勧めです。また、国内各地には海外から様々な文化が導入され増え続けている時代です。テーマパークは非日常なので日本上陸以降も異国のものであることが意識に残りやすい一方で、大型ショッピングセンターやカフェなど日常生活に一部になっているものの中には、海外の発祥地で長い歴史と文化を形成してきた企業の店舗があります。真の意味での交流とは言えないかも知れませんが、調べてみると意外と興味深く楽しめます。
競争と共存
戻る
ことわざの解説を読むと「一見」は自分の目で見ること、と書かれています。旅をして実際に見てみる、観光はむしろ広く観る意味合いがあるようにも思います。新鮮な特産品、本場の料理を食べてみる、と拡大解釈しても良いでしょう。一方で、ことわざで一期一会というと意味合いが違ってしまいますが、旅先で地元のヒトと「一会」するためには少し意識してみることが必要になります。展示物と出会うために行く博物館や美術館でヒトと出会える確率は低そうです。ボランティアや学芸員の方による展示解説に合わせて訪れると少し確率が上がりそうです。地元の市場は、特産品とともに地元の方と出会えそうです。
提携協定と交流会
戻る
博物館では、各分野で価値のある物品や資料を収集、保管、研究し、展示されています。その対象により、総合博物館、科学博物館、歴史博物館、美術館博物館(美術館)、野外博物館、動物園、植物園、水族館などに分類されます。平成27年度の文部科学省社会教育調査によると、これらの中で来館者が多い順としては、歴史、美術、科学博物館、動物園、水族館と続きます。歴史博物館は施設数も圧倒的に多く、動物園と水族館を除くと、施設数と来館者数は概ね対応しているように思います。個人的には国内外を旅行した際に時間が許せば、古代史、自然史、技術史などが揃っている総合博物館に立ち寄るようにしています。各都道府県を代表する博物館、あるいは海外の主要都市の総合博物館に行った際にとても興味深いことは、多かれ少なかれ必ずと言っていいほど石器時代の遺跡出土品が展示されていることです。また、その地域での古くからの生活様式がジオラマなどで表現されていることもあります。地元の博物館へはなかなか足が向きにくいのですが、各地域の良いところを意識するきっかけとしてとても良い入口だと思います。
百聞は一見に如かず
戻る
地域間を移動するのに必要な経費の順番です。自動車、列車、船舶、航空機と移動手段はどんどん便利になっていますが、ヒトが移動するには経費と時間が掛かってしまいます。一方、地域内の近隣同士の交流は勿論とても大切ですが、他地域–外国も含め、情報を集めることについては経費も少なくとても便利になりました。各地域を良い形で維持してより豊かに発展してゆくためには、他を同じ目線で見る、何かを感じる、自を同じ目で見る、他のために何を見せられるか、他に比べて何が贅沢か感じる、安売りをしない、自慢をしない、情報を発信する。
入口は博物館
戻る
ヒトが集中している地域では交流は容易ですが、元々モノは不足しています。なので、情報を駆使して他地域の特産品を運びます。ここでの特産品はヒトが集中している地域で不足しがちなモノを指していて、高級品のことではありません。近頃、特に国内の各地域を旅して感じるのは、地元の特産品が必ずしも安くないことです。他地域に安売りされているのが原因のような気がしています。次に外国とのモノの流通を考える必要があります。既に国内生産では賄いきれないモノも沢山あります。外国から運ばれて来るモノも高級品ばかりではありません。外国の特産品も安売りされているのでしょうか。
• 情報<モノ<ヒト
戻る
植民地時代が終わった現代においては、所謂南北問題と言われるような格差が問題になっています。各地域は独立しています。ヒトとモノが各地域間を行き交っています。戦争は減っているので、武力の比較によって有利、不利を捉えることが難しくなりました。ても、働き盛りのヒトや特産品がある地域に集中することによって、経済的な有利、不利の地域差が明らかになってきています。また、ヒトとモノの地域差により情報の地域差が生まれ、経済格差を加速しているように思います。
• 交流を深めて情報共有、特産品を安売りしない
戻る
子供は自分が住んでいる地域が全てですので、そもそも地域というものを意識することはありません。他地域のヒトとの交流や物流がなかった時代には、大人も地域を意識する必要はありませんでした。
しかし、すごく大雑把に時代の推移を捉えると、近隣地域との関わりが生まれ、更に今では全世界の各地域との交流をポジティブに推進することもできる時代になりました。そのような現代における競争と共存という課題を基盤として、各地域が良い形で維持され、より豊かに発展してゆくための方策を改めて深く考えてみたいと思いました。
• 情報の多寡と時間差
戻る