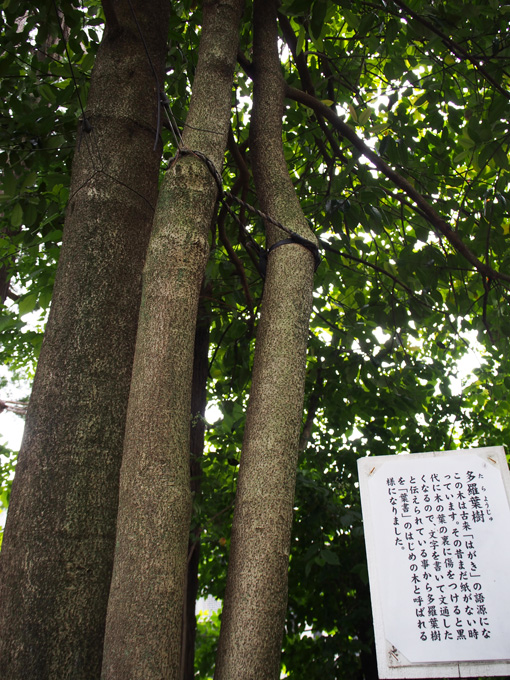目黒区自由が丘1丁目、駅前のロータリーから北に向かってお洒落な商業施設が並ぶ道路を5分程度歩くと、こんもりとした鎮守の杜があります。入口には社号碑と石造りの一の鳥居が、更に進むと二の鳥居と木造の三の鳥居が迎えてくれます。

熊野神社は、かつて「谷畑」といわれた現在の自由が丘、緑が丘一帯の氏神様であり、拝殿は昭和47年に再建されたものですが、朱色の美しい社になっています。

拝殿から渡り廊下で繋がっているのは神楽殿で、秋に催される目黒ばやしは百数十年の歴史を誇るとされています。

拝殿の右手を進むと、江戸時代に建造された境内社の稲荷神社があります。

立派な社殿には龍の彫刻が映えます。更に木鼻には圧巻の獅子の彫刻が施されています。

明治時代以降、大正、昭和にかけて目黒・世田谷の変遷は目覚ましいものでしたが、この熊野神社が現存する地域には、栗山久次郎翁がいらっしゃったということです。

米国のペリー提督が黒船で浦賀沖に来航した頃の生まれの方で、30歳代前半にこの地域の村長になられました。地域の耕地整理事業を進められた他、地名を「自由が丘」とし、発展基盤を築かれたということです。