沖縄は明や清と積極的に交流をもち、また日本とも交易を盛んに行ってきたと云います。一方で沖縄自体は農耕を主な産業としつつ、中国と日本の影響を強く受けそれらの良いところを取り入れつつ、如何に独自の文化を創出して発展させて行くか行政レベルでも尽力してきました。それが我々も広く認識し現代にも続いている、沖縄らしさを感じる風俗、民工芸、技術・芸術力なのだそうです。
琉球王朝の隆盛期は当時の中国、日本と上手く付き合いながら、周囲諸島の統一も進めてきたのですが、やがて転機がやってきます。江戸幕府も黒船来訪に代表されるように欧米諸国の活動の影響を受けましたが、彼等は当然のことながら王朝の存在も無視することはありませんでした。また、薩摩藩も以前から交易相手としてだけではない、支配的な関係性を模索しました。そのような経緯の中、税収の基幹であった農業の不振、交易も一時赤字化するなど、王朝の力が低下してきていました。
日本は明治維新を迎え、沖縄は一時琉球藩と呼ばれるようになりましたが、1879年(明治12年)、遂に琉球王朝の尚氏は首里城を明け渡し、沖縄県となりました。先述の通り、日清戦争やその後の大戦においても、沖縄は国家間の勝敗に左右される立場に置かれながら、現代の状況にあるということです。
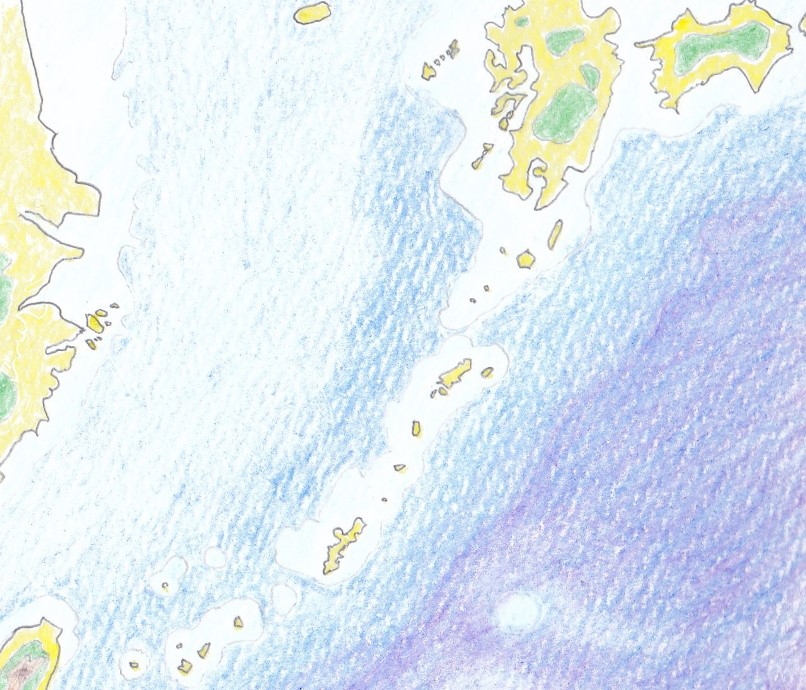
興味深かった点がいくつかあります。明治政府の下、沖縄県の県令としてリーダーシップを取った県外出身者の一部は、ある時期、沖縄の独自性よりもやや強制的に改革を進めようとしたようです。そのような場面では、留学などの経験を経て県政に参画しつつあった沖縄県出身者が活躍したとの記述があります。また、戦後の米国支配下にある時期、20年間に亘って琉球政府が存在したこと、その中で沖縄の人達は本土復帰への活動を続けていたとされています。限られた情報の中での想像ですが、沖縄の人達は、如何に自分達が個性のある存在であるかを内面に持ち続け、対外的にはそれをソフトに表出する、とても強い意志を持った県民であることを表しているような気がしています。
沖縄から話題を日本全体のことに変えますが、少なくとも30年以上前の昭和の時代、日本は島国であることから、その国民は国境を日々意識することもなく、国際感覚が不足していると言われていたように認識しています。一方で、本州などより小さな島国であった沖縄の県民は、過去においても、現代においても、必要に迫られて国際感覚がとても研ぎ澄まされているのだとすれば、島国という言葉、そしてそれを一絡げにするのは全く意味がないことのように感じています。





