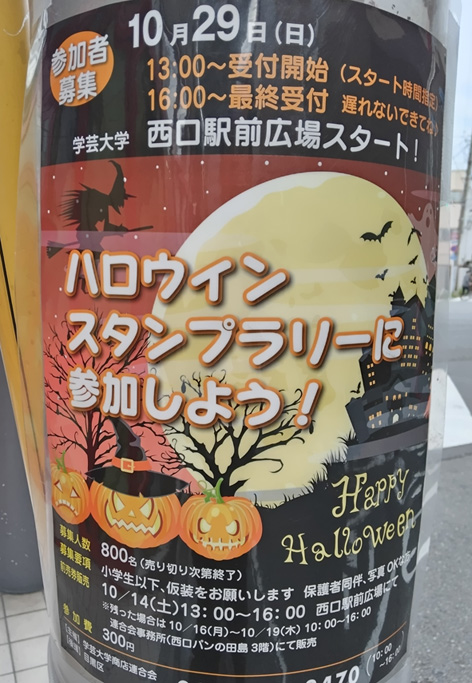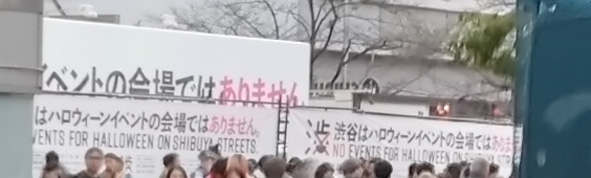先ずは、この正月、1月1日に能登半島地震にて被災された方々のご冥福をお祈りし、お見舞いを申し上げます。今回の地震を含め国内で起こった種々の災害において、各地方自治体は、警察、消防の機能をベースに救援・救護対応が進めてきています。災害の規模により自治体単位で対応しきれない場合もあるため、警察関係では「広域緊急援助隊」、消防関係では「緊急消防援助隊」の機能により相互に応援対応する体制が敷かれています。良く知られていることだと思いますが、通常時は警察、消防は自治体単位で活動しているため、都道府県境を超えて、お隣の緊急車両が入ってくることはありません。但し、都道府県を跨って移動する鉄道においては、それらの管轄を越えて移動警察という形で活動する例外はあります。ただ、こと大災害への対応については、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて体制が整備されました。
災害における救援・救護体制として、警察・消防の活動に加えて、近年とても注目されているのが自衛隊の活躍です。自衛隊法83条「災害派遣」において、「災害派遣都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる」と定められています。自衛隊もしくは自衛官は、重機を用いる大規模な対応を含めて自己完結型の救護・救援を行うことができ、自衛官を目指す若い方たちの志望動機としても、災害派遣を通して人に役立つ仕事がしたいとの声が多いと聞いています。
昨年9月、田原総一朗氏が「自衛隊の高校」に関する記事を公開されています。神奈川県横須賀市にある「陸上自衛隊高等工科学校」を取材された内容です。内容の主題とは異なりますが、私自身は当該高校の教育部長の方の「国内には警察があるが、国際社会には警察がない。自らの努力で国家の主権、領土、国民の安全を守るしくみの必要性を教えている」というご発言が印象に残りました。私自身、もう何十年も前のお話ですが、防衛大学校への進学を考えて、地域の募集案内所を訪れ、桜の焼き印が入った常用饅頭を頂きながらご説明を聞いたことがあります。人の役に立ちたいという気持ちと国防、両者の相互関係は切り口により密接に関係する、あるいは関係しない内容ですが、自衛隊、自衛官の存在が気になる方々がいらっしゃることは理解できますし、大切なことだと思います。
自衛隊の駐屯地は奈良県を除く各都道府県に設置されています。暮らしている地域に自衛隊がない、知り合いに自衛官がいない等、日頃身近に感じづらい方々も多いかと思います。2023年3月において全国に227,843人、他の専門職、例えば医師数が34万人程度とされているのと比較して、それ程かけ離れた数字ではないようです(勿論、必要数に対する多い、少ないを考慮していない比較ですが…)。災害時の自衛官の方々のご尽力に感謝しつつ、その存在について様々な視点から思いを致したいと考えています。